Blog
福島市の不動産・土地・家の相続: 手続きと費用のすべて

親御さんが高齢になり、近い将来に福島市の実家の不動産(土地や家)を相続する可能性があると考えると、不安になりますよね。
初めての相続では、何から手を付ければよいのか分からず、「相続にどんな費用がかかるのか」「手続きの流れはどう進めるのか」と心配になる方も多いでしょう。また、「相続税はどのくらいかかるのか」「不動産を売却するならいつが良いのか」といった疑問もあるかもしれません。
本記事では、福島市で不動産(土地・家屋)を相続する際の費用と手続きについて、最新の法改正や福島市の実情も踏まえて包括的に解説します。
不安になりがちなポイントを整理し、相続税や相続登記、今後の不動産の活用方法までわかりやすく説明します。この記事を読むことで、相続に関する疑問を解消し、具体的に何をすべきかが明確に理解できるようになるでしょう。
福島市の不動産相続にかかる費用の全体像

まず、不動産の相続で発生し得る主な費用を把握しましょう。大きく分けると次のような項目があります。
・相続税 — 相続財産に対して課される国税(該当する場合)
・登録免許税 — 不動産の名義変更(相続登記)時にかかる税金
・不動産取得税 — 不動産を取得した際に課される地方税(相続の場合は原則非課税)
・その他の費用 — 相続登記の手数料(司法書士に依頼する場合の報酬)、各種証明書の発行手数料、遺産分割協議書の作成費用(実費)など
以下でそれぞれ詳しく見ていきます。
相続税の基礎知識:課税の有無と福島市のケース

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産総額が一定の基礎控除額を超える場合にのみ課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求めます。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人なら法定相続人は3人なので、基礎控除額は4,800万円になります。遺産総額がこの額以下であれば相続税はかかりません。
日本全国で見ると、実際に相続税が課税されるケースは全体の1割程度です。2022年の統計では、死亡者約156.9万人のうち相続税が課されたのは約9.6%(10人に1人)に過ぎません。
つまり、多くの場合、不動産や預貯金など遺産の合計額が基礎控除内に収まれば相続税の申告・納税は不要です。特に福島市は東京圏に比べ地価や不動産評価額が抑えられる傾向があるため、一戸建て住宅と預貯金程度の相続であれば非課税となるケースがほとんどです。
しかし、遺産総額が基礎控除を超える場合には相続税の申告が必要です。相続税率は遺産の規模に応じて段階的に上がり、課税遺産総額が多いほど税率も高くなります(最大55%)。
例えば、法定相続人が1人(基礎控除3,600万円)のケースで遺産が5,000万円あると、課税対象額は5,000万円−3,600万円=1,400万円となり、この部分に対して税率10~15%程度から課税されます(細かな税額計算は省略します)。
また、一見「自宅の土地建物だけだから相続税は関係ない」と思われる方も、生命保険金や退職金の支給によって課税ラインを超えるケースもあります。思わぬ現金収入があると相続税が発生する可能性がありますので、遺産の全体像を把握しておきましょう。
なお、配偶者が相続する財産については、配偶者控除(1億6,000万円まで、または法定相続分相当額まで非課税)という特例があります。
例えば、お父様が亡くなりお母様が自宅不動産を相続する場合、お母様には相続税は基本的にかかりません(よほど高額資産でない限り)。そのため一方の親から配偶者へ相続する際は税負担を心配しすぎる必要はないでしょう。
ただし、二次相続(残る親が亡くなった時)では配偶者控除が使えなくなり課税対象となり得ます。将来的に相続税が発生しそうな場合は、早めに税理士など専門家へ相談し、生前贈与や生命保険の活用など節税対策を検討することも大切です。
相続税の申告・納付には期限があります。被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に税務署へ申告と納税を行わなければなりません。例えば1月6日に亡くなった場合、その年の11月6日が申告期限になります。
期限を過ぎると延滞税や無申告加算税などペナルティが科される可能性がありますので注意してください。相続税が発生しそうな場合は、遺産分割の協議中であってもまず10か月以内に申告だけは済ませることが重要です。
不動産の相続登記にかかる費用(登録免許税など)
不動産を相続したら、所有者名義の変更登記(相続登記)を行う必要があります。相続登記の際には登録免許税という税金がかかります。これは不動産の登記手続きをする際に納める税で、相続の場合は不動産の固定資産評価額の0.4%(千分の4)と定められています。
例えば評価額1,000万円の土地家屋を相続登記する場合、登録免許税は約4万円となります。登録免許税は相続税とは別に、不動産ごとに発生する登記のための費用(実費)です。
現在、この登録免許税については小規模な土地に対する免税措置があります。相続で取得した土地の評価額が100万円以下であれば、通常0.4%課される登録免許税が非課税(免税)となります。
この特例は令和7年(2025年)3月31日までの時限措置で、2024年現在、全国どの土地でも適用可能です。福島市内でも、郊外の山林や農地など評価額が低い土地については登録免許税がかからないケースがあります。
ただし、免税になるかどうかは固定資産評価額で判断され、市役所の固定資産税課税台帳に登録された価格が100万円以下かどうかで決まります。該当する場合は登記申請書に免税措置の適用を受ける旨を記載し、必要書類を添付することで税金が免除されます。
相続登記自体にも費用がかかりますが、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されました。従来、相続登記は義務ではなく放置されるケースも多かったのですが、今後は相続が発生してから3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
大切な不動産の権利関係を明確にするためにも、相続登記は早めに済ませるようにしましょう。
登録免許税以外に、不動産の相続に関連して不動産取得税を心配される方がいるかもしれません。しかしご安心ください。相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は原則として課税されません。
取得税の課税対象には「相続」が含まれておらず、亡くなった人から相続人が不動産を承継した場合は非課税となる旨が法律で定められています。
これは「被相続人の死亡によりやむを得ず財産を取得する相続人にまで不動産取得税を課すのは適当でない」という税制上の配慮によるものです。したがって、親から子へ普通に相続するケースでは不動産取得税の心配は不要です。
なお、例外として、法定相続人ではない人(親族以外)が遺言によって不動産を受け取った場合や、生前贈与で不動産を譲り受けた場合などは不動産取得税の課税対象となります。ですが、通常の親族間の相続であれば取得税の負担は発生しません。
その他の費用:登記手続きや専門家への依頼費用など
相続に関連して発生するその他の費用も把握しておきましょう。主なものは次のとおりです。
・相続登記の手続き費用(司法書士報酬):
相続登記を自分で行うこともできますが、必要書類の収集や申請書の作成に不安がある場合は司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士に依頼した場合、報酬(手数料)が発生します。
相続内容や不動産の数によりますが、数万円から10万円程度が目安です(不動産の数や難易度によって増減)。この報酬とは別に、前述の登録免許税や書類取得代などの実費がかかります。報酬額は各事務所で異なるため、依頼前に見積もりを出してもらうとよいでしょう。
・必要書類の取得費用:
相続手続きでは多くの証明書類を集める必要があります。それぞれ発行手数料がかかりますが、一通あたり数百円程度です。
例えば、戸籍謄本(全部事項証明)は1通450円(※福島市の場合)、住民票の除票は300円、固定資産評価証明書は1通あたり数百円程度です。福島市役所や各市町村の窓口で請求できます(郵送請求も可)。
戸籍は被相続人の本籍地で取得しますが、本籍地が福島市の場合は市役所市民課で発行可能です。相続人の戸籍謄本や印鑑証明書はそれぞれ各人の住所地の市区町村役場で取得します。
必要書類の具体的な内容は後述しますが、戸籍類や証明書の発行手数料は総額でも数千円~1万円程度と考えておけば良いでしょう。
・遺産分割協議書の作成費:
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を承継するか決めて遺産分割協議書を作成します。これは自分たちで作成可能ですが、内容に不安があれば司法書士や弁護士にチェック・作成を依頼することもできます。
その場合の費用は専門家の報酬として数万円程度かかる場合があります。協議書には収入印紙は基本的に不要です(相続登記のために提出するだけなら印紙税非課税とされています)。
実印を押して相続人全員の印鑑証明書(各人300円程度)を添付する必要があるため、印鑑証明書の取得費用も人数分かかります。
・その他の専門家費用:
相続税の申告が必要な場合には税理士に依頼することもあります。税理士報酬は遺産総額や相続人の数によりますが、数十万円単位になることもあります。ただし相続税申告はご自身でも可能ですし、税額が比較的少額であれば税理士費用をかけずに済ませる方もいます。
また、不動産の売却を検討する際には不動産仲介手数料(後述しますが、売買価格の3%+6万円が上限の目安【宅地建物取引業法】)がかかる点も念頭に置きましょう。
以上のように、不動産の相続には様々な費用が発生します。しかし相続税や不動産取得税といった大きな税負担はケースによっては不要であり、主な支出は登録免許税と専門家への依頼費用になることが多いです。
事前にどのくらい費用がかかりそうか概算し、不安な場合は専門家に見積もり相談してみると安心です。
福島市で土地・家を相続する手続きの流れと必要書類

次に、福島市における不動産(土地や家屋)の相続手続きの流れを具体的に見ていきます。相続手続きは大まかに以下のステップで進めます:
1.相続人の確定 — 戸籍をたどって法定相続人を全員洗い出します
2.遺言書の確認・検認 — 遺言書が残されていないか確認し、自筆遺言があれば家庭裁判所で検認します(公正証書遺言ならそのまま有効)
3.遺産分割協議 — 相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます(相続人が一人だけの場合や遺言で指定されている場合は不要)
4.必要書類の収集 — 相続登記や相続税申告に必要な戸籍・証明書類を集めます(後述のリスト参照)
5.相続登記の申請 — 管轄の法務局(福島地方法務局)に不動産の名義変更登記を申請します
6.市役所への届出 — 福島市資産税課へ「現所有者申告書」を提出し、固定資産税の納税者名義を変更します
7.相続税の申告・納付(該当者のみ) — 相続税が発生する場合は所轄税務署で申告納税します(期限:10か月以内)
8.各種名義変更 — 銀行口座や株式、自動車など不動産以外の資産も含めて名義変更等の手続きを行います
それでは、各ステップをもう少し詳しく解説します。
1.相続人の確定と戸籍の収集

相続が発生したら最初に行うべきは「相続人の確定」です。これは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍)謄本を取得し、法律上の相続人が誰と誰かを確認する作業です。
戸籍をたどることで、配偶者や子どもはもちろん、万一子どもが先に亡くなっていた場合の孫、認知していた子、前配偶者との間の子など、漏れのない相続人の把握ができます。
被相続人の本籍地が福島市であれば、福島市役所市民課で「戸籍謄本」「改製原戸籍」「除籍謄本」など必要なすべての戸籍類を取得できます(本籍地が他市町村の場合はその役所に請求します)。
戸籍は相続手続きの基本資料となるため、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集めておきましょう。また、相続人全員の現在の戸籍謄本もそれぞれ取得します。これは相続人であることの証明や、後述の相続関係説明図の作成に使用します。
相続人が確定したら、3か月以内に相続放棄や限定承認をするかどうかの判断も必要です(必要な場合)。相続放棄とは相続人の地位を放棄する手続きで、プラスの財産もマイナスの財産(借金等)も一切受け継がない選択です。
家庭裁判所に申述し、認められれば初めから相続人でなかったことになります。例えば、不動産が老朽化して価値が乏しく管理負担のみ大きい場合や、借金が多い場合などは放棄を検討するケースもあります。
ただし放棄すると他の財産も受け取れなくなるため慎重な判断が必要です。期限の3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、この期間内に家庭裁判所へ申述しないと自動的に相続を承認したものとみなされます。なお、相続人全員が放棄すると不動産は国庫帰属も視野に入りますが、特殊なケースなので本記事では割愛します。
2.遺言書の確認と遺産分割協議
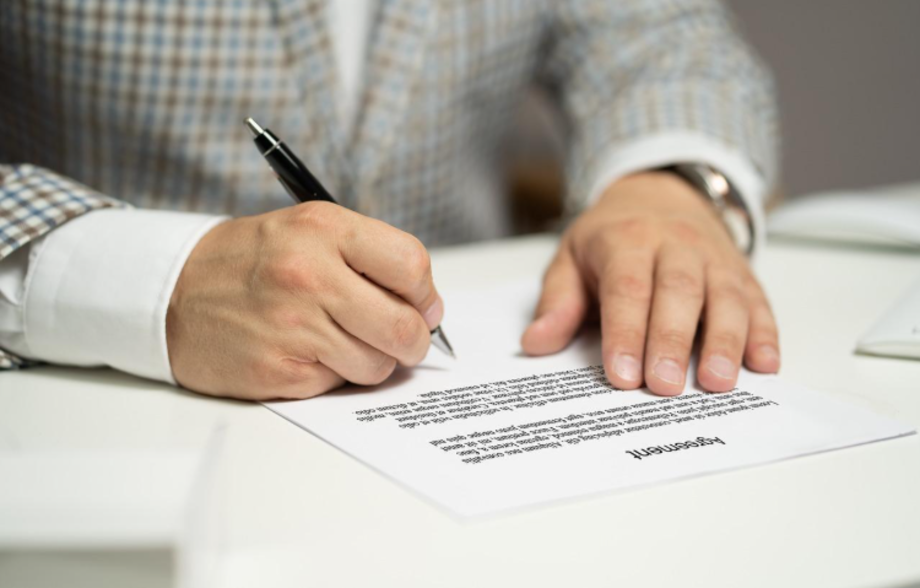
次に、被相続人が遺言書を残していないか確認します。公正証書遺言なら公証役場で原本が保管されていますし、自宅から自筆の遺言書が見つかる場合もあります。
自筆証書遺言が発見されたら、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります(遺言書の形式や内容を確認し、偽造改ざんを防ぐ手続き)。2020年以降、自筆証書遺言を法務局で預かる制度(自筆証書遺言保管制度)も始まっており、預けられた遺言書は検認不要となりました。
いずれにせよ、有効な遺言書がある場合、その内容が相続において最優先されます。たとえば「自宅不動産は長男に相続させる」等の指定があれば、基本的にはその通りに名義変更手続きを進めることになります。
遺言書が無い場合や、遺言で指定されていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、「誰がどの財産を相続するか」を話し合って決めることです。
相続人が複数いる場合、遺産分割協議がまとまらないと相続登記を進めることができません。特に不動産は分割が難しい財産なので、「自宅は長男が取得し、その代わり他の相続人には代償金○○万円を支払う」など具体的な取り決めを全員で合意する必要があります。
円満に話し合いが進むよう、相続人間で十分にコミュニケーションをとることが大切です。
話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」という書面を作成します。協議書には相続人全員が実印で押印し、各自の印鑑証明書を添付します。
協議書の書式に決まりはありませんが、不動産の表示(登記事項どおりの所在・地番・家屋番号など)や誰が取得するかを明記し、日付と署名押印をします。不動産の表示については、法務局で発行される登記事項証明書(土地・建物の登記簿謄本)を写して記載すると確実です。
司法書士に依頼する場合は協議書のひな型を用意してもらえますし、自分で作成する場合でもインターネット上に雛形が公開されていますので参考にするとよいでしょう。
もし相続人間で協議が整わない場合、最終的には家庭裁判所に調停や審判を申し立てて解決を図る方法もあります。ただ調停は時間も費用もかかるため、できれば話し合いによる円満解決を目指したいところです。
専門家を交えての話し合い(司法書士や弁護士に中立的立場で立ち会ってもらう等)も有効でしょう。
3.必要書類のリストと入手方法(福島市での取得先)
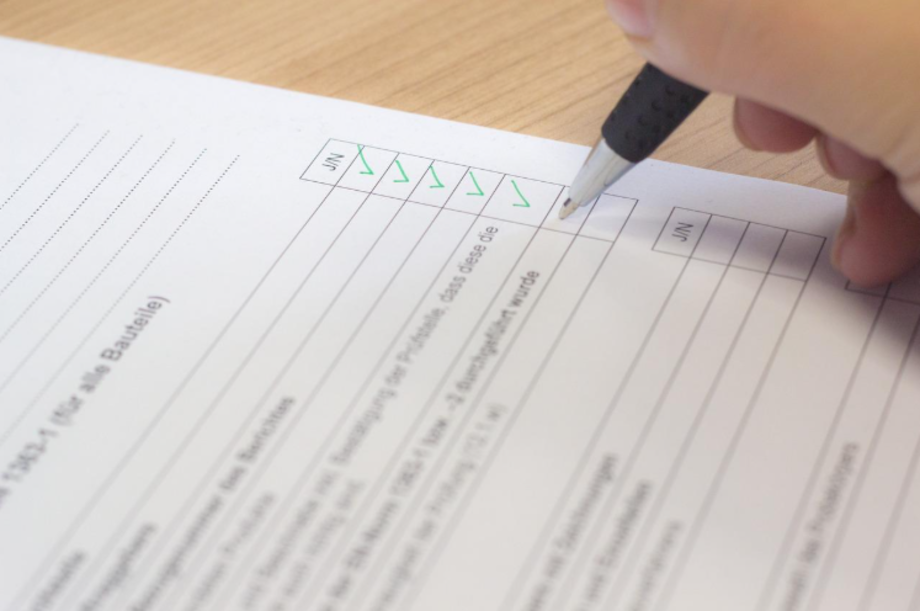
相続登記や各種手続きには、多くの証明書類を提出・添付する必要があります。ここでは代表的な必要書類の一覧と、その入手先についてまとめます。以下は遺産分割協議によって不動産を相続する場合の主な必要書類です。
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式(除籍・改製原戸籍を含む)
入手先:本籍地の市区町村役場(被相続人が福島市本籍なら市役所市民課)
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
入手先:最後の住所地の市区町村役場(福島市に住民登録していた場合は市民課)
・相続人全員の現在の戸籍謄本
入手先:各相続人の本籍地の市区町村役場
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した実印の証明)
入手先:各相続人の住所地の市区町村役場
・相続する不動産の固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書の写し)
入手先:不動産所在地の市区町村役場(福島市資産税課) ※固定資産税課税明細書(納税通知書)でも代用可
・遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印押印したもの)
入手先:相続人で作成(必要に応じ専門家がサポート)
・相続関係説明図(任意)
入手先:相続人で作成 ※戸籍の内容を図式化した家系図のような書面。提出すれば戸籍謄本類の原本を戻してもらえる利点があります。
・登記申請書(相続登記用の用紙)
入手先:法務局窓口でもらうか、自分で作成(法務局HPに様式あり)
・登記事項証明書(登記簿謄本)(任意提出)
入手先:法務局(全国どこでも交付可) ※不動産の正確な地番や家屋番号を確認するために取得。登記申請書への記載ミスを防げます。提出自体は必須ではありません。
・収入印紙(登録免許税用)
入手先:法務局窓口や郵便局等 ※登録免許税額分の印紙を購入し、登記申請書に貼付します。
上記は基本的な書類です。ケースによっては、遺言書がある場合はその写しや検認調書謄本、相続放棄した人がいる場合は家庭裁判所の相続放棄受理証明書、住宅ローンが残っている場合は金融機関との相談資料などが追加で必要になることもあります。一般的な相続登記では上記リストを揃えれば十分です。
書類の取得先について補足します。戸籍類や住民票除票は市区町村役場の窓口で請求します。福島市役所の場合、市民課または各支所・行政サービスコーナーで発行可能です。
郵送で請求することもできるので、遠方にお住まいの方は市役所のホームページから郵送請求書の様式をダウンロードして申請すると良いでしょう。固定資産評価証明書は福島市資産税課(本庁舎2階などに窓口あり)で取得します。
請求には不動産の所在地番が必要です。納税通知書が手元にあればその「課税明細書」に評価額が載っているため、登記にはそれでも代用できます。
印鑑証明書は各相続人が住民登録している自治体で取得します(印鑑登録が必要)。たとえば福島市在住の方なら市民課または支所で発行、県外在住の相続人は各自の市役所等で取得してもらいます。協議書に押した印鑑が実印であることを証明するため、全員分を用意しましょう。
必要書類が揃ったら、書類一式を相続登記の申請時に提出します。戸籍類は原則原本提出ですが、先述の相続関係説明図を添付すれば戸籍類は原本還付(返却)してもらえます。大切な戸籍を手元に戻したい場合は説明図も作成すると良いでしょう。
4.相続登記の申請(法務局での名義変更手続き)

必要書類が揃ったら、いよいよ相続登記(不動産の名義変更登記)を申請します。福島市にある不動産の場合、管轄の登記所は福島地方法務局です。
所在地は福島市五老内町(福島市役所からそれほど遠くない場所)で、電話番号は024-534-2045(登記部門直通)となっています。平日の8時30分~17時15分が窓口受付時間です。直接持参して申請するほか、郵送で申請書類を送ることもできます。
相続登記申請書には、不動産の表示(土地なら所在・地目・地積、建物なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積)や、相続人(登記名義人)となる人の氏名住所、登記の原因(日付)等を記載します。原因日付は通常「令和○年○月○日 相続」とし、被相続人が亡くなった日を指します。
添付書類欄に先ほど集めた戸籍類や協議書等をリストアップし、登録免許税額を記入します。登録免許税は不動産ごとに評価額×0.4%なので、複数不動産がある場合は合計額の印紙を貼ります。
書き方に不安がある場合、法務局の窓口で記載例をもらえますし、福島地方法務局のホームページにも相続登記の記載雛形が掲載されています。
司法書士に依頼している場合は、司法書士が代理で申請してくれるため、相続人自身が法務局に出向く必要はありません。自分で申請する場合は、法務局窓口に提出すればその場で形式のチェックをしてくれ、不備があれば指摘されます。
不備がなければ受理されて登記手続きが開始されます。登記が完了するまでの期間は通常1~2週間程度です。完了後、登記識別情報通知(昔の権利証に相当するもの)や原本還付書類が交付されます。
注意点として、2024年4月1日以降は相続登記が義務となり、放置すると罰則の対象となります。相続開始から3年以内が申請期限とされていますので、義務化前に相続が発生して長年ほったらかしだったケースも含め、早めに登記を済ませましょう。
「忙しくて3年では間に合わない…」という場合、一応正当理由があれば猶予される可能性もありますが、基本的には期限内の申請を心がけましょう。
「忙しくて3年では間に合わない…」という場合、一応正当理由があれば猶予される可能性もありますが、基本的には期限内の申請を心がけてください。義務違反の場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。
5.福島市役所への「現所有者」の届出

相続登記が完了したら(あるいは並行して)、福島市役所への届出も忘れずに行いましょう。不動産の所有者が変わった場合、固定資産税の課税台帳上の名義変更手続きが必要です。
2023年4月から全国で導入された『現所有者申告制度』により、相続等で不動産の所有者が変わった場合は、市町村への申告が義務付けられています。福島市もこの制度に基づき、相続人に申告書の提出を求めています。
具体的には、福島市役所財務部資産税課に「現所有者申告書」という書類を提出します。被相続人の死亡後、資産税課から相続人の代表者宛てに申告書が郵送されてくるので、必要事項を記入し返送すれば手続き完了です。
郵送されるのは相続人のうち代表者お一人だけですので、他の相続人には届かないことに注意してください。もし相続人全員が県外在住で福島市からの郵便物が届かない、あるいは待てど申告書が来ないという場合は、資産税課に連絡して送付を依頼するか、福島市公式サイトから申告書様式をダウンロードして提出しましょう。
現所有者申告書には、亡くなられた方の氏名や死亡日、相続人代表者の氏名住所、相続した不動産の所在地などを記入します。遺産分割協議書がある場合は写しを添付します(協議中で未確定の場合は申告書のみ提出)。
提出期限は特に定められていませんが、市から発送された場合は案内に従いできるだけ早めに提出します。もし提出しないまま放置すると、市の方で職権で現所有者代表を指定する措置が取られます。さらに正当な理由なく提出しないと、市税条例に基づき10万円以下の過料が科される場合があります。
これは相続登記義務化の罰則とは別に、固定資産税の届出義務として課される可能性があるものです。相続登記をしただけでは市役所には通知されませんので、必ず現所有者の届出も完了させましょう。
なお、相続があった年の固定資産税は既に被相続人に課税されています。その年の納税義務は法律上、相続人へ引き継がれることになります。
例えば、被相続人がお亡くなりになった年の固定資産税納税通知書も相続人宛てに送られてきます。相続人代表者がまず立て替えて納付し、相続人間で負担調整する、といった対応が必要になるでしょう。翌年度以降は新しい所有者(相続登記した名義人)に課税されます。
6.相続税の申告・納付(必要な場合のみ)

前述のとおり、相続税の申告・納付が必要な場合は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います。該当者のみの手続きですが、期限がシビアなので他の手続きと並行して進める必要があります。相続税申告には、遺産総額や各人の取得財産を計算し申告書を作成する作業が必要です。
税務署に提出する書類としては、相続税申告書のほか、財産目録、各種控除の明細書、不動産の評価明細など多岐にわたります。
自力で対応が難しければ税理士に依頼しましょう。福島市内にも相続税申告に強い税理士事務所が複数あります。初回無料相談を受け付けている事務所もありますので、不安であれば早めに相談することをおすすめします。
特に不動産を多く相続したケースでは、評価額の算定や特例適用の判断が専門的です。例えば、小規模宅地等の特例(一定要件を満たす宅地の評価額を最大80%減額)などを適用すると大幅に節税できる場合があります。
このような特例も10か月以内の申告が必要です。期限を過ぎると適用できなくなる控除・特例もあるため注意してください。申告期限内に現金納付が難しい場合は延納・物納の制度もありますが、認められるには条件があります。
繰り返しになりますが、相続税が発生しない場合はこれらの申告手続きは不要です。基礎控除内に収まるケースでは税務署に何も出さなくても問題ありません(※念のため税務署に「○○の相続につき申告不要と思われます」等の届出をする方もいますが、義務ではありません)。
相続税がかかるかどうか微妙なラインの場合は、財産評価額を試算してみて、基礎控除を超えるようなら専門家に相談すると良いでしょう。
7.その他の名義変更手続き

不動産以外にも、相続が発生すると様々な名義変更が必要になります。代表的なものを挙げておきます。
・預貯金口座の名義変更・払戻し(各金融機関所定の相続手続き。戸籍や遺産分割協議書が必要)
・証券口座や株式の名義書換え(証券会社や発行会社で手続き)
・自動車の名義変更(軽自動車は市町村、それ以外は運輸支局で手続き)
・電気・ガス・水道などライフライン契約の名義変更
・携帯電話契約の解約または名義変更
・クレジットカードの解約
・公的年金の受給停止手続き(年金事務所へ死亡届出)
・生命保険金の請求手続き(保険会社へ請求。所定の受取人がいれば遺産と別扱い)
特に不動産と金融資産は相続手続きの中心となるので、これらを忘れずに進めましょう。金融機関での相続手続きには、相続人全員の署名捺印が揃った書類や戸籍類一式が要求されます。
不動産の相続登記に使った戸籍類は基本的に転用できますので、一度集めた戸籍はコピーを取っておくなどして他の手続きにも役立てましょう。
相続した不動産をどうする?(活用・売却・賃貸の選択肢)

無事に不動産の名義を相続人へ変更できたら、その相続した不動産を今後どう管理・活用するかを考える段階になります。
親から受け継いだ家や土地を「そのまま自分(相続人)が住み続ける」のか、「売却して現金化する」のか、「賃貸に出して収入を得る」のか——選択肢はいくつかあります。それぞれメリット・デメリットがありますので、自身の状況に合わせて検討しましょう。
住み続ける場合(自分や家族で利用する)

相続した実家に自分や家族がそのまま住む場合、比較的シンプルです。新たに家を買う必要もなく愛着ある家で暮らせることが最大のメリットでしょう。ただし留意すべき点もいくつかあります。
まず、維持管理費を確保しましょう。戸建てであれば定期的な修繕(屋根・外壁塗装や水回り修理など)やリフォーム費用が将来的にかかります。親世代が長年住んでいた家は築年数も経っていることが多く、大規模リフォームが必要になるケースもあります。また、引き続き固定資産税を毎年納める必要があります。
固定資産税額は物件の評価や立地によりますが、福島市内の平均的な住宅地であれば土地と建物で年数万円~十数万円程度が目安です。
居住用家屋には敷地面積200㎡まで評価額1/6に減額される特例が適用されていますので(小規模住宅用地の特例)、実際の税額負担感は評価額ほど大きくないかもしれません。
ただし相続人が別の場所に住んでいる場合(つまり相続した家に住まず空き家にしている場合)はこの住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税負担が数倍に増えることがあります。自分が住むかどうかで税額も変わる点に注意しましょう。
次に、空き家にしないことが重要です。相続人自身が住む意思がなく「とりあえず誰も住まないまま放置」というのは避けるべきです。人が住まなくなると家は急速に傷みます。換気や通水が行われず湿気がこもり、シロアリ被害やカビの発生、建物の劣化が進行します。
また、治安や衛生面でも問題が生じます。管理されていない空き家は近所トラブルの原因になることも多く、倒壊の恐れ、景観の悪化、不審者の侵入、害虫の繁殖、悪臭・火災リスクなど様々なリスクがあります。
福島市でも今後空き家の増加が予想されており、2030年には空き家率が15.1%に達するとの予測もあります。社会問題化している空き家ですが、一つ一つは個人の相続に起因しています。空き家を放置しないことは近隣や社会への責任でもあります。
そのため、相続した家を自分で使わないのであれば、売却や賃貸など他の活用策を検討することを強くおすすめします。「将来子供が戻ってくるかもしれないから、とりあえず維持しておこう」と思う方もいるでしょう。
しかし、その「とりあえず」の期間に家屋が老朽化してしまえば、結局住めなくなり解体費用が発生する…というケースも珍しくありません。どうしてもすぐには手放せない事情がある場合は、最低限定期的な換気や清掃、草刈りなど維持管理だけは行ってください。
遠方にお住まいで頻繁に来られない場合、福島市内の空き家管理サービスを請け負う業者に依頼する手もあります(月額数千円程度で巡回・点検してもらえます)。
自分で住み続ける場合のまとめとしては、愛着ある実家を引き継げる反面、維持費や税負担を自分で負うこと、将来的な修繕計画を立てておくことが大切です。
資産価値という観点では、築古物件の場合は今後下がっていく傾向が強いですが、生活の拠点として価値を見出すのであれば金銭的価値以上のものがあるでしょう。
売却する場合(相続不動産を現金化)

相続した不動産を売却する選択は、多くの方が検討するところです。特に、相続人自身がその不動産に居住しない場合や、遠方在住で管理が難しい場合、売却によって現金化し相続人間で分配するのは合理的な解決策です。売却を検討する際のポイントや流れ、税金面での注意点を押さえておきましょう。
売却までの基本的な流れは以下のとおりです:
1.不動産会社に査定を依頼する
複数の信頼できる不動産会社に現地を見てもらい、市場価格の目安を査定してもらいます(無料査定)。福島市内には地域密着の不動産会社が多数あり、相続不動産の相談を積極的に受け付けている会社もあります。
複数社の査定額を比較し、売却戦略の提案内容や担当者の対応なども踏まえて仲介を依頼する会社を決めます。
2.媒介契約の締結
選んだ不動産仲介会社と媒介契約を結びます。一般媒介(複数社に依頼可)か専任媒介(1社に集中依頼)か選択します。遠方にお住まいなら専任媒介で1社に任せた方が進捗管理しやすいかもしれません。
3.販売活動(買主探し)
不動産会社がレインズへの登録、広告掲載、見込み客への紹介、現地案内など販売活動を行います。相続した家が古い場合、「建物あり」で売るか「更地にして」売るか判断が必要です。
福島市の場合、立地によっては古家付きでも買い手がつきますが、老朽化が激しいと解体更地の方が売りやすいこともあります。解体費用との兼ね合いで仲介担当者と相談しましょう。
4.購入希望者との交渉
買いたい人が現れたら価格や条件の交渉です。提示額より値下げを求められることが一般的ですので、許容ラインを決めておきます。条件がまとまれば売買契約へ進みます。
5.売買契約の締結
売主(相続人)と買主との間で不動産売買契約を締結します。重要事項説明を受け、契約書に署名押印します。買主から手付金を受領します。
相続人が複数いる場合、共有名義で登記されているなら全員が契約の当事者になります。遺産分割で特定の一人に名義をしている場合はその人が売主となります。他の相続人にも事前に了解を取っておきましょう。
6.決済・引き渡し
契約後、通常1か月前後で残代金の決済と物件引き渡しを行います。不動産会社や司法書士立ち会いのもと、買主から残金を受領し、同時に所有権移転登記の申請(買主名義への登記)を行います。
固定資産税の清算(年度途中で名義が変わるため日割り精算)や、鍵の引き渡しもこのタイミングです。
7.仲介手数料等の精算
売却代金を受け取ったら、不動産会社へ仲介手数料を支払います(契約時半額、決済時半額というケースもあります)。また登記関連の実費(司法書士費用)や測量・解体費用等があれば精算します。残った金額が最終的な手取り金です。
売却代金は相続人間で分配します。遺産分割協議で「不動産を売って得たお金を○等分する」と取り決めてあれば、その通りに分配します。不動産が共有名義だった場合も、持分割合に応じて分けます。
売却に際して留意すべき税金があります。まず、売却によって譲渡所得が出た場合、所得税・住民税が課されます。また、譲渡損失が出た場合でも確定申告を行うことで損益通算等の控除制度を活用できることがあります。
ただし取得費(もともとの購入代金等)や譲渡経費(仲介手数料等)を差し引いた残りが課税対象です。親からの相続だと取得費が不明なケースもありますが、その場合でも概算取得費(売却代金の5%)を見做しで控除できます。
特に覚えておきたいのが、被相続人の居住用財産を売却した場合の特例と取得費加算の特例の2つです。
・被相続人居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除:
これは、亡くなった親が一人で住んでいた住宅を相続し、一定の要件を満たして売却する場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
適用要件として、被相続人が亡くなる直前まで一人暮らしだったこと(同居人なし)、建物が昭和56年5月31日以前に建築された古い住宅であること、相続開始から3年以内(正確には3年を経過する日の属する年の年末まで)に売却することなどがあります。
簡単に言えば「高齢の親が亡くなって空き家になった古い家屋を早めに売却する場合の税優遇」です。適用されれば譲渡益から最大3,000万円が非課税枠となるため、ほとんどのケースで譲渡税がゼロになります。
ただしすべての住宅が対象ではなく、区分マンションや耐震性のある住宅などは除かれます。福島市でもこの特例を活用して古い空き家の売却が進んでいるようです。
例えば築40年の一戸建てを相続し、土地建物を1,000万円で売却しても、3,000万円控除内に収まるため所得税・住民税はかからないというイメージです。適用には市役所で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、確定申告で税務署に申告します。
・取得費加算の特例:
こちらは、相続により取得した財産を売却した場合に納めた相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できる制度です。
適用要件は、相続で財産を取得した人に相続税が課税されていること、かつ相続開始から3年10ヶ月以内(= 相続税申告期限から3年以内)にその財産を売却していることです。
平たく言えば、「相続税を払って手に入れた不動産を早期に売った場合、相続税分を経費に入れて譲渡益を減らせる」というものです。
例えば相続税を200万円払って取得した土地を売った場合、譲渡所得計算上200万円を追加の取得費として差し引けます。これにより譲渡益が小さくなり、結果として譲渡所得税が軽減されます。
取得費加算は先述の3,000万円特別控除とも重複適用可能です(両方の要件を満たせば両方使えます)。相続税を支払うほど資産価値の高い不動産なら、この特例も是非検討したいところです。適用する際は確定申告で所定の計算明細を提出する必要があります。
以上の税特例を駆使すれば、相続不動産を売却しても税負担をかなり抑えることができます。特に被相続人が居住していた家を売るケースでは3,000万円控除の有無で大違いですので、対象要件に当てはまるかどうか専門家と確認してください。適用期限は令和9年(2027年)末まで延長されています。
売却に関してもう一つ考慮すべきは「売却のタイミング」です。相続直後にすぐ売るか、しばらく様子を見るか悩むかもしれません。
一般的には、上述の税特例が使える「相続後3年以内」の売却が有利とされています。時間が経つと家屋の老朽化が進み、市場価値が下がる恐れもあります。
福島市の不動産市況を見ると、ここ数年は住宅地価格がわずかながら上昇傾向にあります(福島市の住宅地は9年連続で価格上昇との調査結果もあります)。
とはいえ東京圏ほどの大幅な値上がりは期待しにくく、人口減少もあるため長期的には値下がりリスクもあります。売り時を読むのは難しいですが、「必要以上に長く持ち続けない」「税特例の期限内で判断する」という基準は持っておくと良いでしょう。
最後に、不動産会社への相談時のポイントです。相続した不動産を売る場合、地元の信頼できる不動産会社に相談するのが近道です。
福島市・郡山市を中心に相続相談や空き家売却を専門に扱う会社もあります。相談時には、「現在の市場相場」「売却にかかる諸費用」「売却する際にリフォームや更地化が必要か」「買い手が付きやすくなる工夫」などを質問しましょう。
複数社に相談しても構いません。不動産会社によって提案が異なることもあります。中には自社で直接買取してくれる業者もあります(仲介ではなく買取の場合、相場より低い価格提示が一般的ですが、早く確実に売れる利点があります)。
複数の選択肢を比較検討し、自分たちにとってベストな売却方法を選ぶと良いでしょう。
賃貸に出す場合(相続不動産を貸して活用)

相続した不動産を賃貸に出すという選択肢もあります。自分は住まないが売るのは惜しい、将来また使う可能性がある、といった場合に有力です。
家や土地を貸すことで継続的な収入が得られるメリットがありますが、同時にオーナー(貸主)としての責任や手間も発生します。
賃貸のメリットは何と言っても家賃収入です。毎月の家賃から管理費用等を差し引いた分が収益となり、固定資産税や維持費を賄ってなお利益が出れば、不動産を持ち続ける経済的意義があります。
また、不動産を手放さず所有し続けることで、将来の地価上昇や有効活用のチャンスを待てるという面もあります。売ってしまうと二度と取り戻せませんが、貸しておけば後で自分や子供が使う選択肢も残せます。
賃貸のデメリットは、やはり管理の手間とリスクです。貸主として賃借人(借主)との契約管理や物件の維持管理をしていかなければなりません。具体的には、入居者募集のための広告や内覧対応、賃貸借契約の締結、毎月の家賃集金、滞納があれば督促、退去時の精算・原状回復など、多岐にわたります。
遠方に住んでいる相続人が自主管理するのは現実的ではないため、通常は地元の不動産管理会社に委託します。管理会社に委託すれば、入居者募集から家賃回収、トラブル対応まで請け負ってくれますが、その代わり管理手数料が発生します。
相場は家賃の5~10%程度です。例えば月額8万円で貸した場合、管理会社に月4,000~8,000円程度支払うイメージです。この費用を差し引いても収支がプラスになるよう賃料設定を検討する必要があります。
また、空室リスクも考慮しましょう。借り手が付かなければ収入ゼロどころか、固定資産税や維持費だけ負担が続くことになります。
福島市の場合、地域によって賃貸需要に差があります。大学周辺や駅周辺は比較的需要がありますが、郊外の不便な立地では借り手探しに時間がかかる可能性があります。
築年数の古い一戸建て住宅をそのまま貸す場合、入居希望者が見つかりにくいこともあります。最近は新築・築浅の賃貸物件が増えており、古い家は敬遠されがちです。そのため、必要に応じてリフォームや設備投資も検討しましょう。
最低限、給湯・水回り設備の点検、畳や壁紙の張替え、エアコン設置など、借主が生活できる状態に整えることが大切です。リフォーム代は初期投資となりますが、賃料に見合う範囲で実施することがポイントです。
賃貸経営を始めたら、毎年の確定申告も必要になります。家賃収入から必要経費(固定資産税、管理委託料、修繕費、減価償却費など)を差し引いた不動産所得に対して所得税・住民税が課税されます。
赤字の場合でも申告は原則必要ですが、他の所得(給与所得等)と損益通算できる可能性があります。税務上は経費計上できる項目が色々ありますので、分からなければ税理士に相談してください。
賃貸に出す場合のまとめとして、次の点を整理しましょう:
・長期保有したい意向があるか
将来的に物件を取り戻したい場合、賃貸は良い選択ですが、貸したが最後二度と自宅として使えなくなる可能性もあります(借地借家法で借主が保護されるため、正当事由がないと契約終了しにくい)。
・採算が取れるか
家賃相場を調べ、管理費や税金を引いてプラスになるか試算する。大幅な改修が必要ならその費用も回収できるか検討。
・管理を任せられる会社があるか
地元で評判の良い不動産管理会社を探し、空家を賃貸に回した実績があるかなど確認する。
もし「やはり借り手がつかなそう」「手間に見合わない」と感じたら、無理に賃貸せず速やかに売却することも選択肢です。
特に空室期間が長引くと、結局維持管理に疲弊して売却…というケースもあります。初めから売却の方針が固まっているなら、早めに売ったほうが得策でしょう。
賃貸以外の活用策として、土地として貸す(駐車場にする、資材置場にする)方法もあります。更地にして月極駐車場にするといった例も福島市内では見られます。
ただ、更地にすると住宅用地特例が外れて固定資産税が6倍近くになる点や、初期整備費用(舗装やフェンス設置など)がかかる点に注意です。収益と税負担のバランスを考える必要があります。
まとめ:相続の不安を解消するために/福島市で利用できる相談先

福島市における不動産・土地・家の相続について、費用と手続きの流れ、さらには相続後の不動産の扱い方まで説明してきました。最後に重要ポイントを振り返ります。
・相続にかかる主な費用は、相続税(課税ケースのみ)、登録免許税(評価額の0.4%)、専門家報酬、証明書発行手数料など。
・相続税は基礎控除内なら非課税で、課税されるのは全体の約1割。不動産取得税は相続では非課税。
・相続手続きの流れは、相続人確定 → 遺言確認・遺産分割協議 → 必要書類収集 → 相続登記申請(法務局) → 市役所への現所有者届出 → (必要なら相続税申告)という順序。2024年から相続登記と市役所届出が義務化され、いずれも怠ると過料(罰則)の可能性あり。
・必要書類は戸籍関係、住民票除票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書など多数だが、一覧を確認しながら一つ一つ取得すれば確実に揃えられる。福島市役所や各役場で取得し、郵送請求も活用する。
・相続した不動産の活用は、「自分で利用」「売却」「賃貸」の3択が基本。空き家の放置はリスク大。自分で住むなら維持管理を怠らず、売却するなら税特例(3年以内売却の3000万控除等)を活用。賃貸は収支計画と管理体制をしっかり検討する。
相続手続きは煩雑ですが、決して一人で悩む必要はありません。専門家や公的機関のサポートを積極的に利用しましょう。また相続に強い不動産業者であれば、それぞれの専門家との間に入りワンストップで進めてくれる場合もあります。
最後に強調したいのは、相続手続きを進めるうえで「早めの行動」と「専門家への相談」が何より重要だということです。親御さんがご存命のうちからできる準備(例えば権利関係を整理しておく、財産目録を作成してもらう、遺言を書いてもらう等)もありますし、相続発生後も速やかに動くことで余計な税負担やトラブルを防げます。
今回の解説を参考に、ぜひ適切なステップを踏んで不安を解消し、福島市の不動産相続を円満に乗り切ってください。
専門家の力も借りつつ、一つ一つ手続きをクリアしていけば、きっとスムーズに相続完了の日を迎えられるはずです。皆様の相続手続きが安心・安全に進むことを心より願っています。

